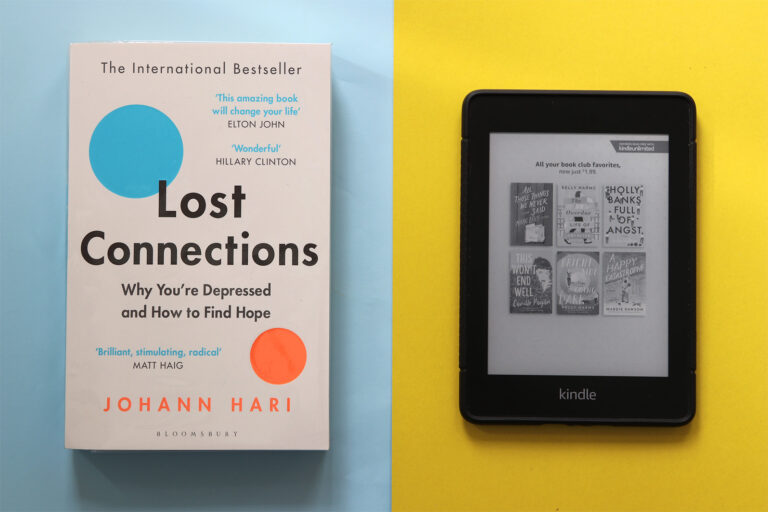いいUIは、いいUXをもたらす(可能性が高い)。
わるいUIは、わるいUXをもたらす(可能性が高い)。
でも、それだけではありません。UXを通り越して、UIはときにぼくらのパーソナリティや文化をも変更させる力(暗黙の影響)を有しています。そしてそれらにより、回顧的に(あるいは“風が吹けば桶屋が儲かる”的に)ぼくらのUXは変化にさらされます。
今回は、プロダクトやサービスの認知前から利用後まで、という通常UXが対象とする範囲をあえて逸脱し、UIの変化がもたらす社会的変化、その結果ぼくらの人生全体のUXの変化について、SF的考察を行ってみます。
俎上に載せるのは、Siriやアレクサ、Googleアシスタントといった「AIアシスタント(スマートスピーカー)」です。
エクリチュールからは逃れられない
本題に入る前にまず、ロラン・バルトの提唱した「エクリチュール」という概念について、大まかに理解する必要があります。
例えば、あなたは目の前の相手に対し、「どんな言葉遣いをするか」を自由に選ぶことができます。地元の方言で話すのか、標準語を用いるのか。敬語で話すのか、それとも横柄に話すのか。その選択は完全なる自由意志です。
※相手が目上の相手だから敬語を使うしかない……という場合でも、強制性はなく、あくまでも敬語を選択したのは自分の意志です。
しかしながら、一度その「言葉遣い」を選択した後には、「その言葉遣いから(自分が)受ける影響」をコントロールすることはできません。
服装についても同じです。休日のあなたは、どんな服を着ることも、どんな服装をすることも、選択的な意味において完全に自由です。
けれど、「その服装をすることによる影響」においては、ただ従うしかありません。そして、言葉遣いも、服装も、その他のあらゆるものは、ぼくらに何らかの影響を与えていることは事実です。
人格を変えたければ言葉を変えるの妥当性
自己啓発書などでは、古典的に「自分を変えたければ言葉を変えよ」と説かれています。エクリチュールの観点からも、この主張は正しいと言えます。
使う言葉や言葉遣いを変える選択は自分でできます。ただその結果、自分に帰ってくる影響は選択不可です。ぼくの人生経験からも、なにかを成し遂げるパワフルな人と、そうでない人とは、やはり選ぶ言葉が違います。
言葉はそれだけ、ぼくらの人格や選択に密接に関わっているという事実については、あなたにも同意いただけるでしょう。
さて、いよいよここからが本題です。
では、「スマートスピーカー」の登場によって、ぼくらの「言葉遣い」はどのように変化し、その代償としてどのような「選択できない影響(エクリチュール)」が発生しているのか。考えたことはあるでしょうか?
外国人に道案内をする
もしあなたが日本で、外国人から「日本語で」道を尋ねられたら、どのように対応するでしょうか。
ふだん家族や友人、同僚と話すのと変わらない調子で話すでしょうか。きっと違うはずです。「外国人に日本語で道を教えるモード」で話すはずです。
丁寧に、ゆっくりと、わかりやすく、やさしく、言葉を伝えるでしょう。わずか一分足らずの出来事かもしれませんが、このときのあなたは、一瞬前までのあなたとは、態度や性格の面では別人です。
態度が変われば言葉遣いが変わるように、言葉遣いが変われば態度(人格)も変わります。
AIアシスタント(スマートスピーカー)に話しかけるとき、ぼくらは同じ状況に陥っています。AIアシスタント(スマートスピーカー)が理解できるように、わかりやすく、独特の文法で、明瞭な声色で、話します。
このとき、ぼくらは普段とは違うエクリチュールの虜囚となっています。
機械語力を持たない世代
日本に生まれ、日本で育つ環境において、英語が話せることはアドバンテージとなり、さまざまな面での可能性が広がることは事実です。かといって、英語が話せないからと死活問題になるわけでもありません。
ぼくの両親は、AIアシスタント(スマートスピーカー)に的確な指示を送り、目的を達成させることが現状できそうにありません。もちろん訓練すれば可能になるでしょうが、これは言い換えれば「AIアシスタント語」が話せない、ということです。
日本語と英語ほど明瞭な差異がないのでわかりにくいですが、AIアシスタントに言葉が通じないということは、AIアシスタント語があり、それらを扱えるかどうかは「スキル」であると言えます。
ただ、このスキル差が今後どんどん拡大していくかというと、微妙なところです。AIアシスタント側が自然言語処理により長けていくでしょうから、将来的にはぼくの両親のように、「いつものように」話す人間の言葉も処理できるようになるかもしれません。
それでも、ぼくら人間側の変化は無視できません。
英語ではなくグロービッシュ
世界公用語的なポジションにある英語は、非母国語話者のほうが圧倒的に多い、めずらしい言語です。
日本でも「社内公用語を英語とする」と発表した企業がありますが、実際は「英語」ではなくもっぱら「グロービッシュ」を指しています。
今さら説明の必要はないでしょうが、「グロービッシュ」とは、非ネイティブ同士が、主にビジネスで用いるためのコミュニケーション・ツールとして、簡易化された英語です。
正確には「グロービッシュの基本単語1500語を使う」「主に能動態を使う」といった、10の基本ルールが存在します。とはいえ、エスペラント語のような人工言語ではなく、あくまで英語の亜種です。
英語がネイティブと非ネイティブの間でグロービッシュに発展したのと同じことが、今度は自然言語の領域で人間と非人間の間で起こる……可能性は否定できません。
音声入力時代にぼくらはぼくらでなくなる
入力インターフェイスとして「音声認識」が主流となれば、ぼくらが使用する日本語も、それに合わせて変化(簡易化)する可能性はゼロではない。
問題はそのとき、どのような「影響(エクリチュール)」をぼくらが受けるのかがわからない、ということです。
ぼくはすでに毎日誰かと対面している時間よりも、独りでモニターを眺めている時間の方が圧倒的に長いです。いいえ、ぼくだけではないでしょう。
それが将来、画面に文字を入力するのではなく、AIアシスタント(スマートスピーカー)に「話しかける」時間の方が長くなったなら、そのときのぼくらが選択する「言葉遣い」は、きっと「これまでのぼくらの言葉遣い」とは異なり、しかしそれが「ふつう」になったときには、ぼくらの人格や文化は、多かれ少なかれ、影響を受けていることは間違いありません。
GAFAMだけの問題ではない
UXの向上、追求は「善」です。その土台は揺らぎません。そのプロセスで、UIの変更を検討し、新たなテクノロジーやデザインが実装されるでしょう。
そのとき、それらを使うか、使わないか、ぼくらは自由に選択することができます。しかしながら、本記事で繰り返し言っているように、その自由な選択の結果から、ぼくらが受ける影響については、ぼくらは一切選択することができません。
無論、AIアシスタント(スマートスピーカー)だけの問題ではありません。ユーザーにこれまでとは違う行動をさせる、習慣づくる可能性のあるUI(インターフェイス)は、普及すればするほど、ぼくらのパーソナリティやカルチャーといった、人生そのものの「経験」に関与する可能性を秘めています。もちろん、わるい意味だけでなく、いい意味においても。
プロダクトやサービスを開発する際、提供側がそのことにも留意することができたなら、社会はより良いもの(未来)になるのではないか。
そうした想いから本記事を書きました。すぐに役に立つ話ではなかったでしょうが、いつかあなたの人生に、いい影響を及ぼすことを願っています。
ではまた。