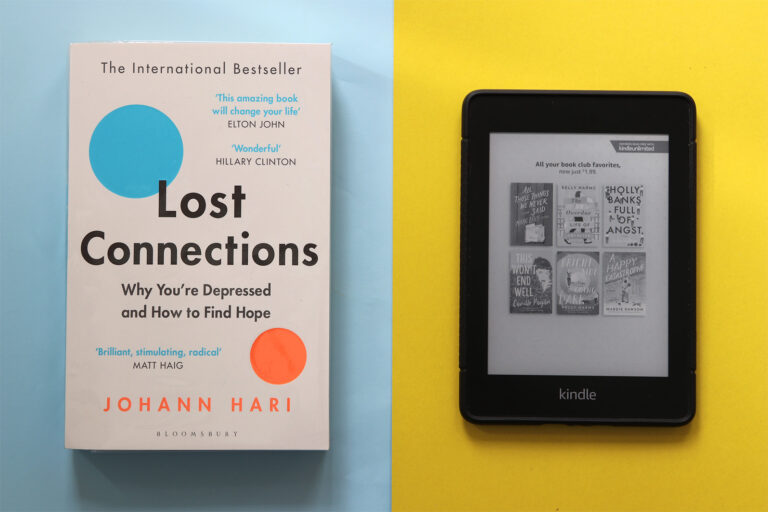ユーザーエクスペリエンスとは、プロダクトやサービスを通じて、ユーザーが得る体験のこと。「UXとは」と検索すると、だいたいこのような解が得られます。
ということは、企業の「UXを重視する」とは、「ユーザーが得る体験を意図的に設計し、実装する」ことだと言えます。
ここで重要なのは、UXの設計も実装も、「事前に」行う、ということです。インタビューを元に、あるいはデータを元に、重要事項を洗い出し、プロダクトやサービスに組み込みます。
ユーザーがそれを実際に「体験」するのは、「そのあと」です。
「なにが言いたいの?」と思われているかもしれませんが、とても大事な前提なので、もう少しだけお付き合いください。
先ほどまでの話を単純化すると、「昨日」までのデータを使って、「今日」実装したUXを、ユーザーは「明日」以降に体験します。
つまり、サービサーとユーザーには「時制のずれ」が発生します。
ユーザーデータを素直に活用し、改善しようとすればするほど、「未来」のユーザーが味わうUXは、サービサーが「今」に最適化するように、「過去」のデータを元に設計・実装されたUXです。
UXを考えるうえで、この事実は非常に重要で、厄介です。
電子書籍と軍手の共通点
定性にせよ、定量にせよ、データを元にするということは、過去を元にするということです。悪いことではありません。そこから改善・解決される課題は山ほどあります。
それでも、データ(だけ)を元にしているなら、PDCAループをどれだけ早めようとも、上述のタイムラグ問題は永遠に解決しません。せいぜい時間が縮まるだけです。
そして、改善アプローチ、最適化アプローチから、驚き(Wow!)や感動(Amazing!)は生まれないとぼくは思っています。ユーザーの驚きや感動がないものは、口コミやバズにもつながりません。現代において、これは致命的です。
サービサーにとって、思いがけない売れ方をした商品に電子書籍と軍手があります。電子書籍は、30-40代のビジネスマン、ガジェット好きがターゲットユーザーで、事実その層にうまくリーチしています。一方で、意外にも高齢者需要が増しているそうです。理由は、文字を大きくできるから。
軍手も、草むしり目当てではなく、手に装着する雑巾として、お掃除グッズとしての購入が増加しています。
意図した(サービサーが設計した)UXとはズレた地点で、想定していないユーザーの体験から、口コミやバズにつながる。電子書籍や軍手でそれが起こったのは、「『過去』のデータを元に設計されたUXではないから」かもしれません。
UXの追求は、会社のM・Vの体現
UXについてはまだまだ問題をなくすだけで精一杯。改善すべき課題が山積み。専任者がおらず、兼務だから優先度が低い……。
などなど、事情はいろいろあるでしょう。しかしながら、もはや「UX」はただのトレンドや課題ではなく、企業の重要な「戦略の一部」です。
言い換えれば、UXの追求は、企業のミッション・ビジョンの体現(表現)であり、そうでなければなりません。そこにファン(ユーザー)がつくかどうかが、企業の生命線であり、生き死にをも左右します。
以上を踏まえて、冒頭の問い、サービサーとユーザーとの間の「時制のずれ」をどう捉え、考えていけばいいのか。
星7の体験を想像(創造)してみる
定性・定量データを元に、現在の課題を解決する「最適化UX」は必要です。ユーザーリサーチや、ユーザーインタビューから、新しいプロダクトやサービスのUXを設計することは、なにもしないより遥かに有用でしょう。
けれど、前述のとおり「最適化UX」は、「未来」のユーザーが味わうUXを、サービサーが「今」に最適化するように、「過去」のデータを元に設計・実装します。
この問題を解消する論理的アプローチは、すべての時制を「未来」にすることです。
米国発、宿泊を民主化したAirbnbの共同創業者、ブライアン・チェスキーの「11-star experience(星11体験)」は大きなヒントになります。簡単に解説すると、Airbnbではまず「星5(5-star)の体験」を話し合います。どういうUXだったら、利用者はレビューで星5をくれるだろうか?
グルメサイトでも、ショッピングサイトでも、通常「星5」が最高評価です。でももし、それを超える「星6」の評価がもらえるとしたら、それはユーザーがどんな体験をしたときだろうか?
そうやって(できる、できないは別に)想像を膨らませていき、最終的に「星11」の体験までイメージを飛躍させていきます(ちなみに、Airbnbでは星11ではイーロン・マスクと宇宙に行くそうです)。
「星11なんて想像もつかない!」というのなら、まずは「星7」くらいでも十分です。想像してみてください。もしユーザーから星5どころか、星7の評価がされるとしたら、それはどんなUXだろうかと。
創造的UXが時制を“未来”にする
過去のデータを元に改善するアプローチを「最適化UX」と呼ぶなら、こうありたいという未来を元に行うアプローチは「創造的UX」と言えるかもしれません。
「創造的UX」は、「未来」のユーザーが味わうUXを、サービサーがこうありたいと願う「未来」を想像し、「未来」を創造するために設計・実装するもの(これで時制が一致します)。
そのとき重要なのは、創造的なUXが「企業のミッション・ビジョンを体現するものである」ということです。繰り返しになりますが、既に「UXは企業戦略そのもの」だからです。
問題点と解決策
とはいえ、「最適化UX」を「創造的UX」に切り替えればいい、という簡単な話ではありません。かといって、両方を切り分けて対応する、ということでもありません。
「最適化UX」によって改善すべきUX上の問題には、きちんと向き合い、対処していく必要があります。それを毎回「創造的UX」により改善しようと思うと、その度に思考の次元を高めていかなければならず、時間も手間もかかります。
現実的には、「最適化UX」としてすぐに対応できるものは、どんどん改善を反映していくべきです。そのうえで、定期的に「創造的UX」のアプローチを考える時間と場所を設け、ユーザーに対して「過去」になっていた時制を「未来」にしていき、そこに企業としてのアイデンティティを表現していく。
それが理想のかたちではないかと思います。
言うは易しで、ぼくら(文殊の知恵)も完璧からはまだまだほど遠い地点にいます。それでも、「11(7)-star experience」をさらに解釈・独自化したような、「創造的UX」を実現していくための有効なアプローチをいくつか持っています。
あなたの組織やチーム向けにアレンジすることもできますので、興味のあるかたは、お問い合わせから気軽にご相談ください。
ではまた。