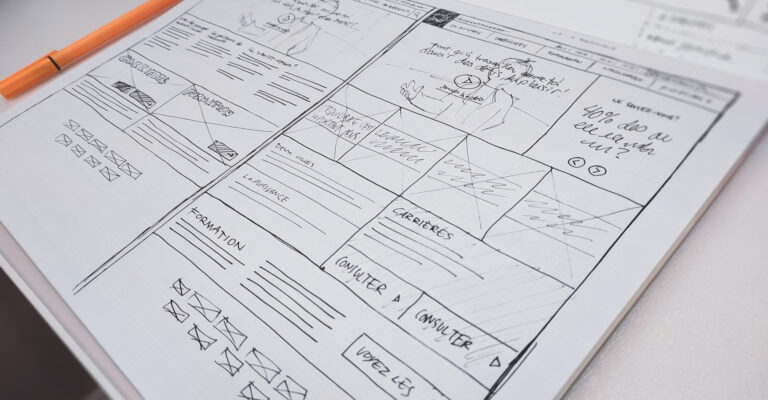仲間と「対話」、してますか?
以前、『雑談マニュアルの有無で対話のUXはどう変わるのか』という記事で、文殊の知恵(UXジャーナルの運営組織)が提供・支援している「対話会」について、ご紹介しました。
今回は対話会で使用する、マニュアルの具体的な内容にふれたいと思います。
脳はつながってこそ
パソコンのCPUは、よく人間の脳に喩えられます。Core i9 など、たくさんの「脳」があるほどパフォーマンスが高くなる。たくさんの並列処理を同時に高速にできる……なんて説明を、聞いたことがあるでしょう。
しかしそれは、それぞれの「脳」が「つながっている」から意味があるわけです。独立して存在していては、連携も、相乗効果も生まれません。
組織でも同じです。どれだけ優秀な人たちが集まっていても、それぞれの優秀な「脳」に、それぞれが自由にアクセスし、能力を引き出すことができなければ、パワーは発揮されないのです。
けれど、こんな「もったいないパワーロス」が、いたるところで起こっています。
でもやっぱり、マニュアルには抵抗が…
そこでぼくら文殊の知恵からの提案が、「対話会」の実施です。雑談の減ってしまった今だからこそ、新しい「つながり」を生むため、互いにどんな連携を持てるのかを知るために、まず「話そう」を第一歩にしています。
「でもそれに、マニュアルって必要?」
と思われるかもしれません。が、ぼくらの答えは「イエス」です。ふだん家族や友人と話すのにマニュアルなんて必要ありません。でも、会社という場、役職や入社歴という先入観が働いてしまう場では、むしろマニュアルがないとうまく機能しません。
20:80の法則(パレートの法則)は、対話の場でも働きます。4、5人以上の人が集まると、たいがい声の大きな2割の人が、会話全体の8割を占めてしまいます。
新しい関係性(と信頼関係)を築き、蜘蛛の巣のように縦横無尽な連携ができる組織にする、という目的で「対話会」をするのなら、できるだけ均等に発言機会があり、誰もが聴くと話すをバランス良く行える場のデザイン(マニュアル)は必須だと考えています。
心理的安全性とオープンな質問
ではいよいよ、マニュアルの中身について。
基本的は「オープニング」「メイン対話パート」「エンディング」の3部構成です。
■オープニング
オープニングの目的は、自己紹介と安全な場づくり。そのため、名前と所属(部署)の後に、必ず「今の気持ち」を共有します。それぞれの参加者が自分の内面(情動)を打ち明けることで、安全で平和な場所であるという認識を持てるようにします。
互いの「強み」を知りたい場合には、「得意なテーマ(ジャンル)」まだ若手なら「得意にしたいテーマ(ジャンル)」を答えてもらうのも効果的です。
また、このときにファシリテーターを決定します。システマチックに決められる方法を用意しておきます。
■メイン対話パート
ここでは、ファシリテーターが一人ひとり順番に、事前に決められた問いを投げかけていきます。問いをどうデザインするかは、会の目的やテーマによって変わります。
共通するポイントは、知識を競わせたり、ひけらかす場ではなく、あくまでも互いのことを知れるような、答える前に内省を促す問いになっていることです。
例えば、「おすすめの本は?」と訊かれると、脳の引き出しの手前にある、最近読んだ面白い本を答えてしまいがちですが(=反応質問)、「人生で一番読み返した本は?」と質問されると、よりパーソナルでその人らしい答えが返ってきやすいです(=内省質問)。
■エンディング
エンディングは、満足感を得つつ、「(また/もっと)つながりたい」「つながれた」という感覚を持っていただくために、再度「今の気持ち」を共有します。そして、今回の感想を伝え合います。
イベントではなく習慣にする
たった一日腹筋をしただけで、ばきばきに腹筋が割れるわけではないように、どれだけ「対話会」に効果があるといっても、一度だけのイベントにしてしまっては期待するだけの効果は得られないかもしれません。
重要なのは、一回のイベントではなく、「対話会」自体を組織の新しい文化、習慣にしていくことだと思っています。
そのためには、開催者(事務局)サイドの負荷を減らし、かつ、会の効果や意義を実感できるような仕組み化や、メッセージの発信も合わせて重要になってきます。
とはいえ、あまり難しく考えず、まずは「やってみよう!」の気持ちで、始めてみてください。こんなに手軽で、コストがかからず、面白いだけでなく長期的に組織を強くする取り組みも、なかなかないんじゃないのとぼくらなんぞは思っております。
では、また書きます。
やるだけの価値はあるし、やるために必要なものは、ほとんどないよ。